2018年09月18日17:19
 DIAMOND online ネット記事
DIAMOND online ネット記事
の転写ですが、とっても大事な内容です。
私の所属する災害動物研究会の入交先生、藤本先生のインタビューも入っていたので要約を転写します。
詳しくは、原文をお読みください。
災害時に「ペットと避難」の実態、最低限必要な備えとは
震災や水害など大規模災害時、ペットは飼い主が連れて「同行避難」するのが大原則だ。ただし、避難先で一緒に生活できるとは限らない。先の西日本豪雨の被災地では、早くからペット同伴者の専用避難所や居住スペースが設けられたが、南海トラフ巨大地震や首都圏直下型大地震で人口密度の高い都市部が広範囲に壊滅した場合、被災者が殺到する避難所でペットと“同居”できる可能性は極めて低い。一時的にせよ、愛犬、愛猫と離れることを想定した時、飼い主は何ができるのだろうか。(医学ライター 井手ゆきえ)
一次避難は同行したけれど……避難所では敷地内別居が現実的
2016年4月14日(余震)、16日(本震)に発生した熊本地震では当初、明確な規則がないまま被災者と被災動物(ペット)が避難所で同居し、さまざまなトラブルが発生した。鳴き声や排泄行為への苦情に遠慮し、やむなく車中泊や半壊した自宅での避難を選んだ飼い主も少なくなかった。
公益社団法人東京都獣医師会危機管理室防災セクション/災害動物医療研究会幹事を務める藤本順介・ふじもと動物病院(東京都三鷹市)院長は、「大都市圏が被災した場合、避難所の数や面積は圧倒的に足りず、被災者すら十分に収容できるとは限りません。被災者のおよそ2割がペットと同行避難すると想定した場合、屋内での“同居”はまず無理でしょう。避難所の敷地内に設けたシェルターでの“別居”が精いっぱいだと思います」と指摘する。
“同居”を優先してしまうと
飼い主の生活再建にも影響が
実際、熊本地震でペットと同居していた被災者からは「犬が鳴き声を上げる度に、周囲をはばかって口を押さえつけていた」「周りにおびえて食欲が落ち、毛が抜けていった」という話を聞く。
これまでの災害経験からも、ペットを飼育していない被災者より、ペットオーナーの生活再建が遅れたという統計が出ている。こうしたもろもろの事実を踏まえると、ペットと家族のためを思えば、まず、人の生活再建を優先し、めどが立ってからペットを迎えに行くという選択肢が現実的なのかもしれない。
“別居”避難を受け入れて
日頃から一時預かりや疎開も視野に
「避難所の敷地内に設けられたシェルターで別居するにせよ、遠方に疎開させるにせよ、避難生活では他のペットたちとの集団生活になること、そして第三者の手に委ねられる可能性を考えておくことが必要です」(藤本氏)。
集団生活を想定した場合、最も気になるのは衛生状態と感染リスクだ。狭く衛生的とはいえない環境でのストレスに満ちた生活は、てきめん免疫力を弱める。集団感染を防ぐためにワクチンを接種していない場合は、シェルター入所に難色を示されるケースもありそうだ。日頃からワクチン接種を心がけておくことが、災害時の安心・安全につながる。
猫は犬とは違い、法律上の縛りはない。しかし、猫の飼い主なら猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス感染症、猫汎白血球減少症や猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ)という病気を聞いたことがあるだろう。災害時の避難生活では、どこでウイルスキャリアの猫に接触しないとも限らない。感染を予防し、また自らが感染源になるリスクを避けるためにも、混合ワクチンの接種は必須だ。
日頃の練習と観察がカギ
コマンド訓練と隠れ場所の把握を
災害動物医療研究会幹事で、米国獣医行動学専門医の入交眞巳氏は避難行動にせよ、避難所での生活にせよ日頃の練習が大事だという。
「犬であれば、日頃から“ハウス”と声を掛けたらキャリーやクレートに入る練習や、“ワンツー、ワンツー”と声を掛けたらシーツに排泄する練習(コマンド・トレーニング)をしておくと、災害時でも慌てずにすみます。キャリーやクレートにおやつを置いて“ここは安全で良いことがある!”と学習させておきましょう」
また“おいで”と呼んだ時に飼い主の側に来たり、リードを付ける練習も必要だ。「犬はもともと首が弱点なので、本来、首周りに触られることを嫌います。まして緊急時のパニック状態の時に無理にリードを付けようとすると激しく抵抗します。こんな時こそ、“おいで”と声をかけて、首周りに触れさせてくれたらおやつをあげ、リードを付けるという日頃慣れた行動をくり返すことで、落ち着かせることもできます」
筆者の家の猫は、まさに呼んでも来ない(?)のだが、猫はどうすればいいのだろう。「猫の場合は何か怖いこと、たとえば知らないお客さんが来たときにサーッと隠れる場所がありますね。その子の“安全地帯”を把握しておいて、抱き上げてキャリーに入れる練習をしてください。特に、地震などの場合はサッシがゆがんで開いた窓から逃げてしまうので、素早くキャリーに、が鉄則です。また万が一を考えて、普段の診察時にマイクロチップを装着しておきましょう」。
「GPSではありませんけれどね」(藤本氏)。追跡はできないが、身元照会には十分だ。環境省はマイクロチップ装着の義務化へ動いており、今年度中に繁殖業者に対する法制度が整備される見込み。言葉を発せない動物たちの電子IDタグとして普及が進んでいる。
分離不安も日頃の治療がカギ
サプリメントや行動療法も
「普段から分離不安が強くて、飼い主さんが居なくなると下痢をしたり、震えが止まらない、無駄ぼえ、過剰な身繕いなど問題行動が見られる時は前もって治療をしておくことが大切です。行動療法や弱い精神安定剤、サプリメントなどさまざまな治療法があるので、かかりつけの獣医さんに相談しておきましょう。その子に合う方法を見つけておけば、いざという時に対応できます」(入交氏)。
ここ数年は、災害時に地域(広域災害の場合は近隣を含む)の獣医師会が組織する災害医療チーム「VMAT:Veterinarian Medical Assistance Team」が避難所を回り、情報の収集や動物救護支援やシェルター管理支援にあたるケースがでてきている。その場で薬をもらうことは難しいが、地域で活動している動物病院やボランティアにつないでもらうことはできる。
第三者を信頼する訓練も
子犬、子猫の時から心がけて
入交氏は「日頃から犬友、猫友ネットワークをつくり、お互いに災害時に声を掛け合うことが大切です」と言う。
被災時に家族がペットの側にいるとは限らない。また、医療関係者や公務員など被災者を支援する立場にある人は、簡単に身動きが取れない場合もあるだろう。そんな際、「迎えに行ってもらったり、現場に行けないまでも、あの子は大丈夫だろうかと気にかけてくれる人を日頃からつくっておくと心強いですね」(藤本氏)。
ウチの子は他人にはなつかなくて……と悩む飼い主もいると思う。
「誰に抱かれても反抗しない、どこに行っても落ち着いている、という行動は子どもの頃の練習なんですね。みんなに見てもらって、抱っこしてもらい“誰かが助けてくれる”という人への信頼をつくることが大切です。大人の犬、猫の場合もある程度は“おやつ”という手段が使えます。お客さんを呼んで、大好きなおやつをあげてもらいましょう。そういう練習をしておくと、どこに行っても、以前とはお散歩コースが違っても“なんとかなる”と自分で納得ができます」(入交氏)。
災害時にペットの身を守るのは、ワクチン接種にせよ、しつけ・訓練にせよ、当たり前だが“普段の飼い方”だ。
ペットの防災グッズをそろえるのもいいが、今一度「ウチの子」がサバイバルできるかどうか、同行避難から避難所での集団生活、第三者の手元での疎開などを含め、現実的にシミュレーションしてみよう。思いがけない落とし穴や発見があるはずだ。
それを日々、修正していけるかどうかが、大規模災害時にペットの明暗を分ける。
災害時の備えとは
カテゴリー │ルナ動物病院
 DIAMOND online ネット記事
DIAMOND online ネット記事の転写ですが、とっても大事な内容です。
私の所属する災害動物研究会の入交先生、藤本先生のインタビューも入っていたので要約を転写します。
詳しくは、原文をお読みください。
災害時に「ペットと避難」の実態、最低限必要な備えとは
震災や水害など大規模災害時、ペットは飼い主が連れて「同行避難」するのが大原則だ。ただし、避難先で一緒に生活できるとは限らない。先の西日本豪雨の被災地では、早くからペット同伴者の専用避難所や居住スペースが設けられたが、南海トラフ巨大地震や首都圏直下型大地震で人口密度の高い都市部が広範囲に壊滅した場合、被災者が殺到する避難所でペットと“同居”できる可能性は極めて低い。一時的にせよ、愛犬、愛猫と離れることを想定した時、飼い主は何ができるのだろうか。(医学ライター 井手ゆきえ)
一次避難は同行したけれど……避難所では敷地内別居が現実的
2016年4月14日(余震)、16日(本震)に発生した熊本地震では当初、明確な規則がないまま被災者と被災動物(ペット)が避難所で同居し、さまざまなトラブルが発生した。鳴き声や排泄行為への苦情に遠慮し、やむなく車中泊や半壊した自宅での避難を選んだ飼い主も少なくなかった。
公益社団法人東京都獣医師会危機管理室防災セクション/災害動物医療研究会幹事を務める藤本順介・ふじもと動物病院(東京都三鷹市)院長は、「大都市圏が被災した場合、避難所の数や面積は圧倒的に足りず、被災者すら十分に収容できるとは限りません。被災者のおよそ2割がペットと同行避難すると想定した場合、屋内での“同居”はまず無理でしょう。避難所の敷地内に設けたシェルターでの“別居”が精いっぱいだと思います」と指摘する。
“同居”を優先してしまうと
飼い主の生活再建にも影響が
実際、熊本地震でペットと同居していた被災者からは「犬が鳴き声を上げる度に、周囲をはばかって口を押さえつけていた」「周りにおびえて食欲が落ち、毛が抜けていった」という話を聞く。
これまでの災害経験からも、ペットを飼育していない被災者より、ペットオーナーの生活再建が遅れたという統計が出ている。こうしたもろもろの事実を踏まえると、ペットと家族のためを思えば、まず、人の生活再建を優先し、めどが立ってからペットを迎えに行くという選択肢が現実的なのかもしれない。
“別居”避難を受け入れて
日頃から一時預かりや疎開も視野に
「避難所の敷地内に設けられたシェルターで別居するにせよ、遠方に疎開させるにせよ、避難生活では他のペットたちとの集団生活になること、そして第三者の手に委ねられる可能性を考えておくことが必要です」(藤本氏)。
集団生活を想定した場合、最も気になるのは衛生状態と感染リスクだ。狭く衛生的とはいえない環境でのストレスに満ちた生活は、てきめん免疫力を弱める。集団感染を防ぐためにワクチンを接種していない場合は、シェルター入所に難色を示されるケースもありそうだ。日頃からワクチン接種を心がけておくことが、災害時の安心・安全につながる。
猫は犬とは違い、法律上の縛りはない。しかし、猫の飼い主なら猫ウイルス性鼻気管炎、猫カリシウイルス感染症、猫汎白血球減少症や猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ)という病気を聞いたことがあるだろう。災害時の避難生活では、どこでウイルスキャリアの猫に接触しないとも限らない。感染を予防し、また自らが感染源になるリスクを避けるためにも、混合ワクチンの接種は必須だ。
日頃の練習と観察がカギ
コマンド訓練と隠れ場所の把握を
災害動物医療研究会幹事で、米国獣医行動学専門医の入交眞巳氏は避難行動にせよ、避難所での生活にせよ日頃の練習が大事だという。
「犬であれば、日頃から“ハウス”と声を掛けたらキャリーやクレートに入る練習や、“ワンツー、ワンツー”と声を掛けたらシーツに排泄する練習(コマンド・トレーニング)をしておくと、災害時でも慌てずにすみます。キャリーやクレートにおやつを置いて“ここは安全で良いことがある!”と学習させておきましょう」
また“おいで”と呼んだ時に飼い主の側に来たり、リードを付ける練習も必要だ。「犬はもともと首が弱点なので、本来、首周りに触られることを嫌います。まして緊急時のパニック状態の時に無理にリードを付けようとすると激しく抵抗します。こんな時こそ、“おいで”と声をかけて、首周りに触れさせてくれたらおやつをあげ、リードを付けるという日頃慣れた行動をくり返すことで、落ち着かせることもできます」
筆者の家の猫は、まさに呼んでも来ない(?)のだが、猫はどうすればいいのだろう。「猫の場合は何か怖いこと、たとえば知らないお客さんが来たときにサーッと隠れる場所がありますね。その子の“安全地帯”を把握しておいて、抱き上げてキャリーに入れる練習をしてください。特に、地震などの場合はサッシがゆがんで開いた窓から逃げてしまうので、素早くキャリーに、が鉄則です。また万が一を考えて、普段の診察時にマイクロチップを装着しておきましょう」。
「GPSではありませんけれどね」(藤本氏)。追跡はできないが、身元照会には十分だ。環境省はマイクロチップ装着の義務化へ動いており、今年度中に繁殖業者に対する法制度が整備される見込み。言葉を発せない動物たちの電子IDタグとして普及が進んでいる。
分離不安も日頃の治療がカギ
サプリメントや行動療法も
「普段から分離不安が強くて、飼い主さんが居なくなると下痢をしたり、震えが止まらない、無駄ぼえ、過剰な身繕いなど問題行動が見られる時は前もって治療をしておくことが大切です。行動療法や弱い精神安定剤、サプリメントなどさまざまな治療法があるので、かかりつけの獣医さんに相談しておきましょう。その子に合う方法を見つけておけば、いざという時に対応できます」(入交氏)。
ここ数年は、災害時に地域(広域災害の場合は近隣を含む)の獣医師会が組織する災害医療チーム「VMAT:Veterinarian Medical Assistance Team」が避難所を回り、情報の収集や動物救護支援やシェルター管理支援にあたるケースがでてきている。その場で薬をもらうことは難しいが、地域で活動している動物病院やボランティアにつないでもらうことはできる。
第三者を信頼する訓練も
子犬、子猫の時から心がけて
入交氏は「日頃から犬友、猫友ネットワークをつくり、お互いに災害時に声を掛け合うことが大切です」と言う。
被災時に家族がペットの側にいるとは限らない。また、医療関係者や公務員など被災者を支援する立場にある人は、簡単に身動きが取れない場合もあるだろう。そんな際、「迎えに行ってもらったり、現場に行けないまでも、あの子は大丈夫だろうかと気にかけてくれる人を日頃からつくっておくと心強いですね」(藤本氏)。
ウチの子は他人にはなつかなくて……と悩む飼い主もいると思う。
「誰に抱かれても反抗しない、どこに行っても落ち着いている、という行動は子どもの頃の練習なんですね。みんなに見てもらって、抱っこしてもらい“誰かが助けてくれる”という人への信頼をつくることが大切です。大人の犬、猫の場合もある程度は“おやつ”という手段が使えます。お客さんを呼んで、大好きなおやつをあげてもらいましょう。そういう練習をしておくと、どこに行っても、以前とはお散歩コースが違っても“なんとかなる”と自分で納得ができます」(入交氏)。
災害時にペットの身を守るのは、ワクチン接種にせよ、しつけ・訓練にせよ、当たり前だが“普段の飼い方”だ。
ペットの防災グッズをそろえるのもいいが、今一度「ウチの子」がサバイバルできるかどうか、同行避難から避難所での集団生活、第三者の手元での疎開などを含め、現実的にシミュレーションしてみよう。思いがけない落とし穴や発見があるはずだ。
それを日々、修正していけるかどうかが、大規模災害時にペットの明暗を分ける。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|








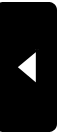
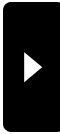
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。